| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |
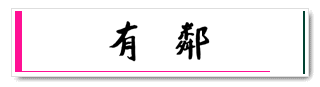
| 平成16年6月10日 第439号 P3 |
|
|
| ○座談会 | P1 | 黒井千次 |
|
| ○特集 | P4 | 新発見の大日如来像と運慶 山本勉 | |
| ○人と作品 | P5 | 伊坂幸太郎と「アヒルと鴨のコインロッカー」 |
|
|
座談会 話題の新人作家たち (3)
|
|
◇独自の世界を持つ女性作家たち |
|
|
| 鵜飼 | 山本周五郎賞のときは、岡山弁で記者会見をやって、おもしろかったですね。 破天荒な感じの、何かが出てきそうな人ですね。
|
|||
| 清原 | ある意味では久しぶりの女文士のような感じがあって、人にどう思われようと勝手だみたいなところがありますね。 でも、『偽偽満州』は、満州へ男を追っていく話なんですが、結構ちゃんと調べているんですよ。 はちゃめちゃに見えて、そういうところはきちっとやっている。 いろんな可能性のある人で、これからまた新しい境地を開拓していくんじゃないかな。
|
|||
具体的なものを積み上げて書く田口ランディ |
||||
| 藤田 | 田口ランディは、最近『富士山』が出ましたが、力のある作家ですね。
|
|||
| 鵜飼 |
彼女が最初に書いた長編小説は『コンセント』という、実話に基づいた作品なんですが、お兄さんがひきこもりになった末に亡くなってしまった。 そのことが人生にどういうふうに形を与えてくるかというのをモチーフにしているんですが、それでは非常に精神的な作品なのかというと、彼女は、ある種の困惑というものを、極めて具体的に書く力がある。 しかも、その人々の持っている悲しみ、悲しみというよりも痛みですね、その書き方が非常に身体の感覚に基づいている。 小説では、えてして想像力というものが大切にされるんですが、ランディさんの想像力は頭の世界の力ではなくて、より即物的でリアルなものです。 生きている人間とのかかわり合いの中で何ができるのかという、非常に具体的なところを積み上げながら書いていくのがいいと思うんです。 |
|||
| 藤田 | ネット作家だったということに関係があるのかもしれないけれども、文章の感性が非常にいいですね。
|
|||
| 鵜飼 | よくわからないことがあると、宙づりにしてあいまいにしてしまいたいところってありますよね。 彼女は、はっきり書けないけれども、少なくとも宙づりになっている状態のところまでしっかり持っていって、読者の中で同じようにもやもやしている痛みとか、困惑とかを、ある種の形として出す力があるのかなと思います。 ただ、まだ構成ということにおいては弱いところがあるようですけれども。
|
|||
人物の扱いがうまい諸田玲子 |
||||
| 清原 | 時代小説でも女性がたくさん出てきている。 その中で目を見張ってよくなったと思うのは諸田玲子ですね。 『其の一日』で吉川英治文学新人賞を取っています。
|
|||
| 藤田 | 清水次郎長の子孫なんですよね。 |
|||
| 清原 |
だけど以前には、向田邦子さんの『阿修羅のごとく』のテレビ脚本のノベライゼーションをやっているんですね。 だから、人物の出し入れがうまいんですよ。 初めは女性が書く任侠小説というので、希少価値というか、奇異というか、そういう感じで受けとめられていたようだけれども、その後いろんなジャンルを書いています。 『其の一日』は4編の作品集で、これで彼女は短編の手法みたいなものをつかんだなという感じがあった。 長編もありまして、例えば『犬吉』は、生類憐みの令で中野に造られたお犬小屋で犬の世話をしている女の子とか下積みの連中がいやいや仕事をやっているんだけど、その朝に赤穂四十七士の討ち入りがあって、みんなが異常に興奮するという話。 お犬様に仕えているという一種の屈辱感が、どういう形で解放されるかというときに、「忠臣蔵」を持ってくる。 あの発想のよさは結構おもしろいなと思っているんですよ。 今までは実験作もあったけれども、だんだん方向性が定まってきたようで、この先が楽しみですね。 最近の時代小説のもう一つの傾向として、諸田さんもそうですが、この10年位、女性が捕物帳を書くんです。 今までは、捕物帳は男の世界だったんですが、平岩弓枝さん以降だと思います。 その典型が『御宿[おんやど]かわせみ』ですね。 ただ女性は、やはりアクション場面は苦手なんでしょうね。 どうしてもホームドラマになってしまうところはありますね。 |
|||
◇経済小説や児童文学からも注目の作家が |
||||
|
|
| でも、佐藤雅美さんの、新田次郎文学賞をとった『大君の通貨』を読んで、なるほどと思ったんですが、よくよく考えてみたら、貿易をするわけですから1ドルが幾らかというレートを、そのときに決めなくてはいけない。 結局、1ドルを1両にする。 そこのところを、幕閣の下にいる小栗上野介だとかの幕臣たちが西欧列強とせめぎ合ってやっていたわけですよね。 そういうおもしろさが、今までの歴史小説の中では余りなかったんです。 |
||||||
| 藤田 | いいところに目をつけましたね。 |
|||||
| 清原 | 幕末には、外交だけじゃなくて、経済的なもの、日米修好通商条約による貿易摩擦や関税の問題、通貨の問題とかもあるわけで、幸田さんはそのあたりもきちっとできるはずなんです。
これまで、経済小説というと、佐藤雅美さん、清水一行さんや城山三郎さん、高杉良さん、やはり男性作家が多いでしょう。 そこへ女性が、それも国際金融の現場にいた人が参入してきて、新しい感覚で書いていくというのはおもしろいと思います。 そういう形でやっていけば、今までの歴史経済小説とはまた違うものがでてくるんじゃないか。 幕末だけじゃなくて、大正モラトリアムとか、明治期の疑獄事件でもいいわけで、題材はたくさんあるはずですからね。 |
|||||
| 藤田 | これからの活躍が期待できますね。 |
|||||
自分の言葉でそれぞれの空気をつくっていく |
||||||
| 鵜飼 |
何人か挙げますと、まず湯本香樹実[ゆもとかずみ]さん。 『西日の町』で一度芥川賞候補になっていますけれども、もともと児童文学から出てきた人です。 子どもをテーマにして書かれていますね。 それから、本屋大賞で第4位の『永遠の出口』を書いた森絵都[もりえと]さん。 この作品では、主人公の女の子の小学3年生から高校卒業までの9年間を9編の短編の連作で描いています。 この人も児童文学から出てきた人で、『カラフル』が知られています。 章ごとに語り手が変わる構成の連作のかたちで家族を描いた、角田光代さんの『空中庭園』は、何か新しい境地をつかまれたなという感じがするし、井上光晴さんの娘さんの井上荒野[いのうえあれの]さんの『森のなかのママ』も、ほんとに何げなく日常の中で生きているけれど、実際にはいろんなことがあって、人生はそれでも続いていくというところを、淡々と描いている。 そういう手づかみできない言葉を、大きい言葉や観念ではなくて書こうとしている作家たちは、これからも注目していきたいですね。 |
|||||
中堅の作家たちにも新しい可能性を期待したい |
||||||
| 黒井 | 今回、芥川賞を二人の若い女性が受賞したこともあって、どうしても女性や、若い作家たちに関心が集まってしまう傾向があると思うんですが、いろいろなことを試みている作家たちは、男性の中にも、それから、すでに賞をとっている人たちの中にもいると思うんですよ。
たとえば、これはちょっと感心したんだけれども、『パーク・ライフ』で芥川賞を受賞した吉田修一が、まだ本にはなっていないんですが、『ランドマーク』という小説を「群像」5月号に書いているんです。 大宮のほうに建てる巨大ビルの建築のことを、現場の作業者と、設計した人間の両方から書いている。 なかなか野心作で、おもしろいと思いました。 |
|||||
| 鵜飼 | 吉田さんの、今の時代の空気をカラリとつかむ文章は、とてもいいですね。 |
|||||
| 清原 | 作風も、どちらかというと地味な感じで、あまり声高に言ってないですよね。 |
|||||
| 黒井 | そういう意味で、表にまだ出ないものまで含めて見ると、なかなか豊かな時代になりつつあるという感じがします。
|
|||||
| 藤田 | 直木賞のほうも、ここ数年の受賞者でいえば、藤田宜永とか乙川優三郎、京極夏彦といった作家たちは、もう今や不動の地位を占めたと言えるとは思うんですが、彼らのこれからの作品も楽しみですよね。
|
|||||
| 鵜飼 | 桐野夏生さんも、ものすごく力量があって、どんどんいろんなものを書いています。 現実の中に生きている人間、とりわけ女性の持っている何かをグイグイ描く。 それから小池真理子さんの耽美性はたまらない。
|
|||||
| 清原 | 江國香織さんも、今後さらに期待したいですね。 まだまだ可能性がある感じがします。 全体的に見ても、かつてに比べたら透明感がある作品がふえていますよね。 そこが、今の若い人たちに受けているのかなとも思いますね。 |
|||||
| 黒井 | 女性も男性も、ベテランも若手も問わず、一時期よりも今、活況を呈してきているという印象はたしかに受けますね。
|
|||||
| 藤田 | どうもありがとうございました。 |
|||||
| 黒井千次 (くろいせんじ) |
| 1932年東京生まれ。 著書『石の話』 講談社文芸文庫 1,260円、 『羽根と翼』 講談社 2,100円、ほか多数。 |
| 清原康正 (きよはらやすまさ) |
| 1945年旧満州生まれ。 著書『山本周五郎のことば』 新潮新書 680円、 『新選組アンソロジー 上・下』 舞字社 各1,890円、ほか。 |
| 鵜飼哲夫 (うかいてつお) |
| 1959年名古屋市生まれ。 |
|