| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |

| 平成16年9月10日 第442号 P3 |
|
|
| ○座談会 | P1 | 横浜美術館・開館から15年 (1)
(2) (3) 雪山行二/浅葉克己/岡部あおみ/猿渡紀代子/松信裕 |
|
| ○特集 | P4 | ばななの日本語 金田一秀穂 | |
| ○人と作品 | P5 | 平野啓一郎と「滴り落ちる時計たちの波紋」 | |
| ○有鄰らいぶらりい | P5 | 高杉良著 「混沌」/丸谷才一著 「猫のつもりが虎」/奥野英朗著 「空中ブランコ」/澤田ふじ子著 「花籠の櫛」 | |
| ○類書紹介 | P6 | 「古代の朝鮮」・・・日本にも深い関わりのある高句麗・新羅・百済の三国など。 |
|
|
座談会 横浜美術館・開館から15年 (3)
|
◇社会的要求も広がり、改革・変身を迫られる |
||
| 松信 |
岡部先生はミュゼオロジーがご専攻ですが、それはどういうことをする学問なんですか。 |
|
| 岡部 |
ミュゼオロジーは、いわゆる博物館学ですが、私がやったのはむしろ美術館学です。 美術館の歴史、国際的なレベルでの比較、現在の美術館のあり方を学び、あるいは、これから先どうなっていくのかとか、それに芸術はつねに動いているものですから、それをどういうふうにシステムに落とし込むか。
また、システムそのものをどう変換できるのかということを大きな視野とヴィジョンで、客観的に研究する学問です。 |
|
| 猿渡 |
美術とか文化の問題が、ただ単に、美術館とか博物館の問題ではなくなっています。 現代美術自体も、博物館や美術館という、いわゆる箱というか、建物のなかで展示したり、何かつくるということだけではなくなってきました。 むしろ、もっと別の場所で、大がかりにインスタレーションが行われたり、あるいは人が参加することによって初めて成り立つ作品とか、終わってしまえば何もなくなってしまうようなものなど、大きく形態が変わっていますから、横浜のまちづくりのなかで、美術館が果たす役割のようなものも、確実に変質をせざるを得ないわけです。 ですから、横浜市のほうも美術館だけではなくて、トリエンナーレをやるとか、あるいは古い銀行の建物を使って展開する「バンカート」といった新しい形の活動を立ち上げているんです。 |
|
美術館の「塀」の外の人たちとどう手を組むか |
||
| 雪山 |
美術館は本当に大きく変わったと思います。 私が美術館に入ったころ、学芸員の仕事というのは、とにかくいいコレクションをつくること、いい展覧会をやること、それに尽きる。 そのために調査研究をする。 それ自身、私は間違っているとは思っていません。 未来の世代に残すべき文化財を公開し、保存するということは大変重要なことだし、美術館活動の根幹だと思っている。 けれども、美術館に対する社会的な要求もどんどん広がってきたし、現代美術も変わってきた。 美術館の役割も、その占める位置も変わってきた以上、美術館も、自分たち自身の改革、変身というのが迫られています。 私は美術館に28年もいて、要するに美術館の塀の内側で暮らしてきた人間です。 それが今、塀の外にたくさんいる非常に優秀な人たち、美術活動を一生懸命やっている人たちとどうやって手を組んでいけばいいのか。
要するに内側に住んでいる人間としては、組み方がわからないというのが率直な感じですね。 |
|
蓄積されたコレクションをどう活用するかが大切 |
||
| 岡部 |
日本の美術館はある意味で急速に進歩しました。 しかも、全国に点在してますね。 この数と、コレクションの蓄積を見てみると、ものすごい量のコレクションが日本にあることがわかる。
ですから、今までと同じように収集活動も大事ですけれど、これからはそれをどう活用するかに目を向け、頭を少し切りかえてもいいように思えます。
|
|
| 猿渡 |
1994年の「モネ展」や2002年の「印象派とその時代展」では国内コレクションが大いに活用されてます。 |
|
| 雪山 |
横浜美術館もいいコレクションを随分持っているんですけれども、もう少し、見せ方に工夫の余地があると思いますね。 展示室の面積が狭いものですから、年に3回展示がえをしているんですけれども、ほんとはいいものはいつでも並べておかないと、美術館のイメージがつくれないんです。
そこに行けば必ずその作品がある。 そういう展示も必要でしょうね。 |
|
ジャンルや時代の枠を取り払いテーマで見せる |
||
| 猿渡 |
横浜美術館では、この春、開館15周年の記念事業の第一弾として「イメージをめぐる冒険」という、コレクション中心の展覧会を行いました。 これまで集めてきたものを、常設展とは別の観点から紹介しましょうということで、開催したものです。 ふだんですと、日本画、日本洋画、写真というように展示室ごとに分けているんですが、そういうジャンルとか、時代とかを全部取り払ってしまって、四つの世界をめぐる冒険に見立てて展示したものです。 たとえば「パノラミックワールド」という空間には広々とした景色を描いたものを並べました。 すると、ダリの大きな絵と國領經郎さんの砂丘の絵とが隣り合わせで展示される。
工藤甲人さんの日本画と、マックス・エルンストの油絵が思わぬ共通点を見せる。 見るほうもそれを発見することができる。 |
|
| 岡部 |
すごくおもしろかったです。 |
|
| 猿渡 |
入場者数は1万8千人でしたが、アンケートを読むと、皆さんがとても楽しんでくださったようなんです。 「こんなにコレクションがあったんですね」とか、こちらの内情を見透かされたような「予算もなくて大変でしょうけど、頑張ってください」などという励ましの言葉をいただいてしまったり。 今年度以降は年に1回ぐらいの割合で、コレクションベースの企画展を開いていく予定です。 |
|
| 岡部 |
ダリの作品も、べつのコンテキスト(文脈)で見られて、再評価し、再確認しました。 テーマで見せていただけると、また別の角度から異なる読解ができます。 |
|
◇シュルレアリスムの作品収集は日本屈指 |
||
| 松信 |
横浜美術館のコレクションのなかで珠玉のもの、お好きなものというとどのような作品でしょうか。 |
|
| 雪山 |
私はやっぱりシュルレアリスムがいいですね。 日本でも屈指のコレクションです。 |
|
| 猿渡 |
ダリとか、マグリットとか。 |
|
| 岡部 |
あと珍しいミロの作品もありますね。 |
|
| 雪山 |
私が一番好きなのは初期のミロです。 「花と蝶」が個人的には好きですね。 |
|
| 岡部 |
初期のミロの作品はとても稀少です。 |
|
| 松信 |
ルネ・マグリットもいいものがありますね。 |
|
| 猿渡 |
その名も、「王様の美術館」という作品があります。 今年度の第三期のコレクション展は11月24日から来年の3月23日までで、テーマはシュルレアリスムです。 この展覧会では、「シュルレアリスム西洋と日本」とか、「シュルレアリスムと写真」とか、「シュルレアリスムと版画」とか、シュルレアリスムオンパレードで、横浜美術館のシュルレアリスムのコレクションを、いちどにいろいろ見ていただけると思います。 来年1月5日からは、企画展のほうも「マルセル・デュシャンと二十世紀美術」を開催しますので、両方合わせてお楽しみいただければと思っております。 |
|
| 松信 | ||
| 猿渡 |
ちょうど今、(11月14日まで)今年度第二期のコレクション展になります、開館15周年記念で購入した小林古径の、果物を描いた静物画を中心に「小林古径と院展の画家たち」の作品を展示中です。
横山大観や下村観山から始まって、次の世代の今村紫紅とか、速水御舟、前田青邨、安田靫彦も含めた展示です。 |
|
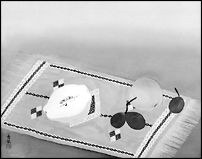
|
|
◇開館15周年記念展 失楽園:風景表現の近代1870-1945 |
||||
| 松信 |
10月9日から12月12日までは、開館15周年の企画展である「失楽園:風景表現の近代1870-1945」が開催されますね。 これはどういう展覧会ですか。 |
|||
| 雪山 |
これは、去年の2月にやりました「明るい窓:風景表現の近代」に続いての、シリーズ第2回展なんです。 この「風景表現の近代」は、これまでのように西洋とか、日本とかに分けて風景画の様式の発展を示すのではなくて、風景とは何かということを考えてもらうというのがねらいです。 つまり、風景はただ単にわれわれを取り巻く環境ではなくて、人間が眼差しを向けることによって初めて成立するものであるということなんです。
今回とりあげる作品は、フランスで印象派が登場した1870年代から、第二次世界大戦が終結する1945年までのものです。 この70年あまりの間の、欧米と日本、そして極東アジアの作品を、大都市の興隆や社会主義思想の影響、近代化と反近代、二つの大きな戦争などの、この時代の社会的・政治的視点からとらえ直そうという趣旨の展覧会です。 題名の「失楽園」は、ちょっと悲観的かもしれませんけれども、結局人間は、楽園を求めながらも、そこから遠く離れざるをえない、そういうテーマの展覧会になると思います。 西洋絵画、日本画、洋画、それからそのコンセプトに合わせた写真などを的確に配置しますので、実際にそれをご覧になれば、どういう意味かご理解いただけるのではないか、なかなかおもしろい展覧会になるんじゃないでしょうか。 たとえば、戦前、台湾や朝鮮から、美術の留学生がかなり日本に来ているんですね。 昔の東京美術学校(現・東京芸術大学)で随分勉強していますし、そういう人たちの絵も借りて展示するとか、あるいは満州に対する日本人の見方を示すとか。 これまでのわれわれの常識になっていた見方からはちょっと外れた視点に立って風景表現を見直そうと、そんなことを考えております。 それから、この時代に発明された映画のなかの風景表現も見ていただこうと、上映会も予定しています。 |
|||
ジャンルを超えた学芸員の活動で新しい展開に期待 |
||
| 猿渡 |
一つつけ加えさせていただくと、横浜美術館はやたら間口が広いと言われることがあります。 特にコレクションは、日本画もあるし、西洋のシュルレアリスムもあるし、写真もあり、現代美術もあるということで、よく言えば総合的ですけれども、分別がないみたいな言い方もされます。
けれど、「風景表現の近代」とか「幕末・明治の横浜展」のような展覧会は、いろいろなジャンルのコレクションをこれまで積み上げてきて、それぞれの調査研究をしている学芸員がいて、初めて成り立つ展覧会ではあるんです。
|
|
| 岡部 |
いつも、すごくいい企画展をなさっているのは、やはり実力のある学芸員の方がいらっしゃるということです。 しかもそうした学芸員の研究をきちんと支えてきた美術館があって、コレクションも非常に豊かですしね。
今、それぞれの学芸員の人たちが自分のジャンルを超えて、一緒にいろいろやっていけるような状況になってきているので、これからの展開もとても楽しみです。
|
|
| 松信 |
どうもありがとうございました。 |
|
| 雪山行二 (ゆきやま こうじ) |
| 1947年冨山生まれ。 著書『ゴヤ ロス・カプリチョス』 二玄社 3,360円(5%税込)ほか。 |
| 浅葉克己 (あさば かつみ) |
| 1940年横浜生まれ。 著書『地球文字探険家』 二玄社 1,890円(5%税込)ほか。 |
| 岡部あおみ (おかべ あおみ) |
|
東京生まれ。 |
| 猿渡紀代子 (さわたり きよこ) |
|
横浜生まれ。 |
|