
※2014/2/28以前の「本の泉」は、5%税込の商品価格を表示しています。 |
| 第1回 2006年5月18日 |
|
背中を押してくれる"あの頃小説" |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
小学生や中学生の頃に戻りたいとは思わない。 なぜなら、あの頃はコミックを大人買いすることもできなかったし、運動会やマラソン大会など参加したくもない行事が目白押しだったし、下校のときに買い食いすることもできなかったからだ。 あの頃と比べると今はなんて自由なのだろう、と晴々と思う。 だが、時々あの頃の不自由さがたまらなく懐かしく思われる時がある。 今の自由を犠牲にしてもいいから、もう一度、曇りのない目で世の中を見つめてみたいと思う時がある。 5月病で悩む方も多いこの時期、新鮮な視点を取り戻させてくれる"あの頃小説"を、今回はご紹介しようと思う。 『夜の朝顔』は、まさに私が必要としていた小説だった。 ミュンヘン五輪、川端康成の自殺、ジャコビニ流星雨をリアルタイムでご存知の方は必読の1冊。 舞台は、1960年代の、フィンランドに限りなく近いスウェーデンの村。 ラジオを聴くためには、庭の松の木のあいだに銅線を張ってアンテナがわりにしなければ受信できないような田舎だ。 この北極圏の厳しい自然の中で、思春期を過ごした少年が主人公。 彼が初めてエルヴィス・プレスリーのレコードを聴いた時の感動が微笑ましい。 「これが未来だ。 未来っていうのは、こういう音がするんだ」。 と言っても、単なる田舎の少年の成長物語だと思ったら大間違い。 思わず失笑してしまうようなオゲレツなユーモアに満ちていて、時には「一族の呪い」なんて怖い単語も登場する。 登場人物たちのアクの強さには北欧人そのものに対する見方まで変わってきてしまうほどだ。 「世界ってどれぐらい大きいの?」 「すごく大きいさ」 「でも、どこかに終わりがあるんでしょ?」 「中国だな」 こんな会話をしている彼らから見たら、日本に暮らす私たちは宇宙人のようなものなのか。 それでも、初めて音楽に触れた時の感動や初めて好きな人と話した時のドキドキをいつまでも大切に思う気持ちは、彼らも私達も一緒なのだ。 懐かしさと喪失感が混ざった最後の1ページには、胸が一杯になった。 今回ご紹介した3冊の中では、最も刺激的な1冊だ(いろいろな意味で)。
文・読書推進委員 加藤泉 構成・宣伝課 矢島真理子 | |||||||||||||||||||||||||||
|
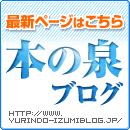
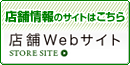
 クリック
クリック








