| |
私事で恐縮だが、私は3人きょうだいの末っ子だ。
しかも両親が年を取ってから生まれた子供なので、上の兄とは10歳、下の兄とは8歳、離れている。
かなりの確率で、自分が両親と兄達を看取ることになるのだろうな、とだいぶ前から覚悟している。
なぜこのような話をするかと言うと、今回ご紹介する角田光代の新刊『夜をゆく飛行機』に次のようなエピソードがあるからだ。
主人公の里々子[りりこ]が小学生だった頃に家族でプールに行った思い出がある。
里々子が泳いでいる間に、家族は彼女の存在に気付かずに帰っていってしまう。
ゆっくりと遠ざかっていく家族を、追いかけることもせずぼうっと眺めている里々子。
その姿が、いつか家族を見送る自分に重なるように思えてならなかった。
本書の舞台は、酒店を営む谷島家。
語り手は4人姉妹の末っ子の里々子。
4人姉妹の物語と言うと、『若草物語』や『細雪』を思い出す方も多いだろうが、本書を読んで私が思い出したのは、向田邦子の『阿修羅のごとく』だ。
ごくごく身近で、面白おかしくて、それなのに人生の悲哀が滲み出ている、そんな物語。
次女の寿子[ことこ]が家族をモデルにして書いた小説が新人文学賞を受賞するところから、本書は始まる。
「なんだかとんでもない厄介ごとのはじまりになるような予感」と里々子が思ったとおり、この小説がきっかけとなって、長女の有子[ありこ]は夫と別居し、合コン好きの三女素子[もとこ]は突然家業を継ぐと言い出し、そして里々子は大学受験に失敗し、つまらない男に恋をする。
谷島一家のやりとりがユーモアに満ちていて、くすくす笑いながら読み進めることができるのだが、伯母の死や祖母の入院を通じて「ひょっとしたら生きていくということは、どんどん何かをなくしていくことかもしれない」と里々子は強く意識するようになる。
そこが本書の肝だ。
どんな人間関係でもいずれは何らかの形で別れが訪れるものだという、普段そうそう意識することのない(あるいは、あえて目を背けている)事実に、読んでいる私たちも里々子と同様、対峙させられる。
前々から思っていたが、角田光代の描く「日常」はいとおしい。
それは、世の中に常なるものなどない、という人生観が背景にあるからだ。
—「私たちのすることは全部、はじめたときから終わっている」。
本書の中に表れる、あまりにも正鵠を射たこのセリフには胸が詰まる。
それでも、日常を生きていくことは無意味なことではない、かけがえのないものなのだ、と慰める力をこの本は持っている。
本書のタイトルは、夜になると物干し台から里々子が見上げる、飛行機の明かりが由来となっている。
そう言えば、夜をゆく飛行機を見送るせつなさは、過ぎていく時間を止めたいと願う時の気持ちとよく似ているかもしれない。
今回は、東野圭吾『赤い指』も、桜庭一樹『少女七竈と七人の可愛そうな大人』も、豊島ミホ『エバーグリーン』もご紹介したかったのだが、『夜をゆく飛行機』があまりにも良すぎたので、この1冊のみ! |
|
まだまだあります!
おすすめ
角田光代作品 |

対岸の彼女
文藝春秋
1,680円
(5%税込) |
| 直木賞受賞作。
女性同士の強い友情を感じさせる1冊。 |
|

Presents
双葉社
1,470円
(5%税込) |
| 人生で受け取るプレゼントの数々。一番大事なのは、贈り物にこめられた思いを受け取ること。 |
|

ドラママチ
文藝春秋
1,350円
(5%税込) |
| 中央線沿線の「マチ」を舞台に、何かを「待つ」女性たちの物語。 |
|
|

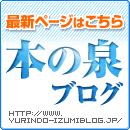
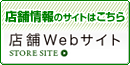
 クリック
クリック



