| |
| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |
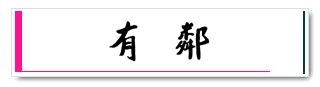
| 平成16年3月10日 第436号 P1 |
|
|
||||
| ○化粧坂の声 | P1 | 藤沢周 | ||
| ○座談会 外国人が詠む 日本語俳句 | P2 P3 P4 | |||
| ○人と作品 | P5 | 綿矢りさと『蹴りたい背中』 | ||
|
|
||||
| 化粧坂の声 藤沢周 |
 |
| 藤沢周氏 |
|
| あれから一度も訪ねていない。 鎌倉・化粧坂[けわいざか]──。 10年ほど前、ふと立ち寄った古刹、円覚寺境内の気にインスピレーションを受け、翌日引越先を決めたのが北鎌倉の地である。風俗店やカジノのイルミネーションが踊る新宿歌舞伎町を舞台に小説を書いていた男が、何故、歴史ある土地に住むことになったのか。理由といっても、本人にも分からない。 宝冠釈迦如来が鎮座する仏殿と、さやかに聞こえる竹林の静寂、胸の奥にまで染み入る緑の匂い、止まった時間……。ただ、その時、私は円覚寺の境内を占める空気を描写しようなどとは微塵にも思わず、染まりたい、同化したいとだけ思ったのだ。つまり、この地で活しろ、という声が何処からか聞こえてきたとしか言い様がない。 円覚寺。建長寺。東慶寺。浄智寺。明月院……。長寿寺。円応寺。浄光明寺。鶴岡八幡宮……。いわゆる、観光マップに載っている寺社群を、それこそ観光客気分で毎日経巡っては、心身に充満する雑念を落としていたのだ。 だが、いくつかのスポットで足が停滞し、気配を微妙に窺わなければ歩けない所もある。むろん、歴史ある土地のことだから、外灯のない夜道を歩いていて、視野の隅に揺れる白い影と何度か遭遇し、「ああ、幽霊か」とひとりごちることはあるにはある。目の錯覚や気のせいとして解釈するよりも、ゴーストの方がこの地では腑に落ちる。 そのような時は、ひたすらに般若心経など胸中で唱えながら無視し、行きつけの呑み屋さんに着いたところで、「出たぁー!」と大声を上げればいい。いかにも、古都鎌倉の日常的挨拶として受け入れられ、酒の肴になり、付いてきた白い影も酔いに揺れて、笑いに溶ける。 人のアナロジーとしての幽霊は、まだそれでもこちらの邪心の表れとも取れて納得するしかないが、そんな冗談が通じない、いや、拒絶するトポスが、鎌倉には存在するのだ。それが、私にとっては、化粧坂なのである。
どの寺も、社も、切り通しも、何度か訪ねているというのに、化粧坂だけは一度しかない。しかも、歩いてから数日経って、そこが化粧坂という一応の観光名所になっていることを知ったのだが。 鎌倉五山第四位の禅刹・浄智寺。年季の入った石段を登ると、花頭窓のある鐘楼門がこじんまりと立つ、私の大好きな寺なのだが、その脇道を行く。いわゆる瓜ヶ谷[うりがやつ]と呼ばれる道である。 その時は、確か、倒木のため進入禁止となっていたのだが、すでに一端の地元民だと誤解していた私は、そのまま狭い山道を上り、葛原岡[くずはらがおか]神社や日野俊基の墓のある源氏山へと至り、何気なく左へと下りていったのだ。 公園化されているにもかかわらず、源氏山自体がある種の霊気と寂しさに満ちてもいるのだが、その坂に入った途端、一気に空気の質が変わるのを覚えた。鬱蒼とした木々のせいか、枝葉に覆われた薄暗さのせいか、とも思う。何処から染み出しているのか、清水に濡れた黒土のにおいが濃くなったが、不思議と草いきれや、あるいは、夏であったはずの蝉時雨の記憶がない。 おそらくは、そこに占められていた気配の方にばかり気を取られていたのだろう。土から露出した太い根の隆起の夥しさ。腐葉土が重なり、墨色と化した土。かなり勾配のきつい坂道を慎重に下りたのだが、背後と脇に異様なほどの何者かの気配を息遣いとして感じたのだ。 「……ここは、やばい……」 科学的にいえば、プラズマらしきものが発生しているともいえるし、歴史的には血で血を洗う惨劇の合戦があった場所だからということもある。どんな渇水状態でも染み出る清水を、「義経の血」と地元の人はいってもいるらしい。 化粧坂という名前の由来も、「木生え坂」の訛りからとか、当時住んでいた遊女達がお化粧をしたからという説もあるが、平家武将の首を化粧して首実検したところから名付けられたという説もある。 いや、だが、坂の名前さえ知らなかった私にとって、ただならぬ気配は、びっしりと結露して全身を覆ってしまう霊の吐息のようであったけれども、むしろ、ここは人と一緒には来てはいけない場所としての怖さを感じたといえばいいか。 まだそれでも独りならばいい。あるいは、親子であるならば、そのまま幽界へと共に連れ立って静かに消え入るということの諧調がある。私が思ったのは、血の繋がらぬ者との同行は危ないという感触だった。特に、異性。ただならぬ関係にある女性との化粧坂、あるいは男との化粧坂……。 突如、自らが狂い出して相手に何かしでかす、殺めるということもあるのではないか。そんな予感が感情の隙に滑り込んできたのだ。ここで、俺は途轍もない精算をしてしまうのではないか……。一体、自分は何を考えているのか、とたじろぎ、黒い地面を這う根の群れを急ぎ足で踏みしめ、息を荒くして下りてきたのを思い出す。 しばらくして後、その坂の名前を知り、鎌倉七切り通しの一つとして国史跡にもなっていることを知った。そして、化粧坂を上る二人、男と女を描いた小説を目にすることになる。
鎌倉在住30年の作家・立原正秋(1926〜80)の長編『残りの雪』である。私はあまり立原を読んでこなかったけれども、女が夢の中で見た化粧坂のシーンに、やはり同じ気配を嗅ぎ取る大先達がいたのだと心の底が震えた。その心といっても、残酷さであり、脆弱さであり、また真摯さでもある。いずれにしても己の心を裸にして、無意識の内で眠る負のエネルギーのようなものを噴出させる引き金が、化粧坂にはあるのだと。 武者達の群れとなって蠢く霊というよりも、地霊(ゲニウス・ロキ)に近いのだろうか。露出し、湿った岩の角の丸みは、天文学的に人の足に踏み込まれた所以だろうし、木の根もまた然り。何処の山にもあるだろう坂道だが、体の内側から巨大な冷たい掌で撫で上げられるようなその地は、おそらく人の持つ無意識の風景でもあるのか。欲望し、喜び、怖れ、悲しみながら、たえず賽の河原のような荒涼を抱える人間の内面の温度が、ひっそりと息を静めている。 まったくの私感には違いない。だが、私が最近、導入部を書き始めたばかりの北鎌倉舞台の長編は、化粧坂の風景が何処かで出てくるに違いないと予感する。現実には、もう二度と行くつもりがない場所であるが、あの坂が私と結んだ黒い糸を手繰り寄せている気がしてならないのだ。 男と女を書け。人間を書け。狂気を書け。光を、闇を、修羅を書け、と。 <死をいとい生をもおそれ人間の ゆれ定まらぬこころ知るのみ> 鎌倉・瑞泉寺にある吉野秀雄の歌碑にはそう刻まれている。 |
| 藤沢周 (ふじさわ しゅう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959年新潟県生れ。 作家。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|