| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |
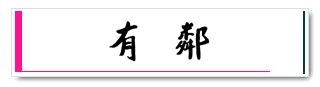
| 平成16年3月10日 第436号 P4 |
|
|
||||
| ○化粧坂の声 | P1 | 藤沢周 | ||
| ○座談会 外国人が詠む日本語俳句 | P2 P3 P4 | |||
| ○人と作品 | P5 | 綿矢りさと『蹴りたい背中』 | ||
|
|
||||
| 座談会 外国人が詠む 日本語俳句 (3)
|
◇クラゲこそ宇宙そのもの |
|
| 藤田 |
リンズィーさんのご専門は海洋生物学で、とくにクラゲに詳しいということですね。 |
| リンズィー |
クラゲこそ宇宙ですよ。 クラゲは海洋にいっぱい出てきて、パーンと溶けていなくなってしまう存在なわけです。 |
| 宗 |
いいですね。 クラゲこそ宇宙ですか。 |
| リンズィー |
クラゲはプランクトンの一種なんですよ。 最も大きなプランクトン。 プランクトンは浮遊生物で、海流に流される命なんです。 魚などは海流に向かって泳いでいけば、ほかのところに行けるんですけれども、プランクトンであるクラゲはそのまま流れていくしかない。 |
| 藤田 |
ものすごく大きいクラゲもいるそうですね。 |
| リンズィー |
世界で一番長い生物は、クジラじゃなくてクラゲなんですよ。 40メートルの長さにもなるアイオイクラゲというのが深海にいるんです。 バイオマスというか、重量にしてみれば全然ちっちゃくて、太さは私の腕ぐらいしかないんですけど、40メートルの長さで、ヘビみたいな形なんです。 流し網のように触手をたらして、死のカーテンを深海でつくって、夜、オキアミとかミジンコみたいなものが表層に上がってきて、植物プランクトンを食べようとするのを待ち構えていて、全部つかまえちゃうんです。 そういう恐ろしい海の仲間を研究しているんですよ。 ただ、俳句では詠めないんです。 いくら深海の中ですごい魚に出会っても、イレズミコンニャクアジとか、ホソワニトカゲギスとかでは、イメージがわいてこないですよね(笑)。 それが困っているところなんです。 |
| 藤田 |
海での句は大分詠んでいらっしゃいますね。 |
| リンズィー |
はい。 「海蛇の長き一息梅雨に入る」は好きなんですよ。 スキューバダイビングをやっているときに、何かすごい音がしたので表層を見たら、海蛇が息を吸っていた。 海蛇は体長の8割が肺なんです。 だから、すっごい一息なんです。
長くスーッと吸うんですね。 それが梅雨に入る時期だったわけです。 |
自然の中の一瞬を詠んで、宇宙を表現してみたい |
|
| 藤田 |
原さんは実際に俳句をつくり、あるいは詩をお詠みになる立場として、リンズィーさんの『むつごろう』などの句をお読みになっての感想はいかがですか。 |
| 原 |
私も最初に宗先生が挙げた3句がいいなと思っていて、「稲妻の光りて時間こはばりぬ」は、その一瞬の中に宇宙があるような気がして大好きです。 それから、「自転車よりもの転げ落ち師走かな」とか、「我が鼻を春の眠りの出で入りつ」の句にはリンズィーさんの冗談好きな顔が覗いていて、思わずくすっと笑えるんです。
先が見えないくらい長い行列を詠んだ「大晦日エスカレーターの先消ゆる」も好きですね。 |
| 藤田 |
きょうのお話も、いろいろと刺激になったんじゃないですか。 |
| 原 |
もっと他者になりきって、自然の中で俳句を詠むように心がけたいと思います。 私も自然の中の一瞬を詠んで、宇宙を表現できるようなものをつくりたいと思っているんですけど、なかなかそれがうまくできないんです。 でも、いろいろお話を聞いていて、イメージがだんだんつかめた感じがしています。 |
| 宗 |
クラゲになりたいと思う気持ちが高まってくれば、きっといろいろな俳句や詩がつくれますよ。 |
| 原 |
そうですね。 |
| リンズィー |
流れていく命というテーマにしたらどうですか。 |
| 宗 |
それはおもしろそうですね。 |
◇外国の俳句は日本に追いつく勢い |
|||
| 藤田 |
俳句のこれからについて、どんなふうに考えておられますか。 |
||
| リンズィー |
外国でも俳句を一所懸命勉強していて、実力のある俳人たちが、どんどんお互いに議論し合っています。 今までは雑誌の上での話だけだったので、非常にペースが遅かったんですけれど、この10年間はインターネットが発達したこともあって、スピード感が出て、すごく盛り上がっているんです。 そういうこともあって、もう日本に追いつくぐらいの勢いになっているんですよ。 日本の人たちも、外国の俳句を見て、取り入れるものがきっとあると思うんですね。 それがいい刺激になったらなと思います。 もう一つ、今注目しているのはオーストラリアのアンソロジーなんです。 南半球で、今までとは逆の季節感を持っている作者たちが俳句をつくっている。 私も南半球の人間なので、季節のとらえ方が、普通の人と違う部分もあるのかなという気がするんです。 日本に住んでいても、冬にキュウリが買えるような世の中なので、その辺を追求してもいいと思って、非常に興味を持って見ています。 現代俳句協会から数年前に出た『現代俳句歳時記』(注)の中で金子兜太が、季語は非常に重要であるということを、ちゃんと言ってくれています。 私としては、内へ内へと見ているだけじゃなくて、外国の俳句を見たり、現代詩も見たりして、いろんなものをどんどん積極的に取り入れて、自分の俳句を強くしたいな思っているんです。
|
||
|
|||
外国の俳句に学びジャンルを超えた交流ができる場を |
|
| 宗 |
僕は俳句全体に対する希望として、二つのことを考えています。 その一つは、外国人から学ぶことだと思うんです。 外国人がつくっているHAIKUは、いわゆる日本の現代俳句とは少し違っているところがあるんですけれども、僕は間違った違い方ではないと思う。 宇宙そのものに学ぼうというおおらかさが、外国人のHAIKUにはあると思うので、そういうところからは、現代の日本の俳人も学ばなくてはいけない。 もう一つは、たとえば俳句について、俳句以外のジャンルの現代詩とか短歌の人が批判する。 さらに現代短歌や現代詩についても同じことをやって、相互批判ができる場をつくるということです。 そういう三者の枠を超えた交流が起これば、そこから現代俳句に対する何らかのよい影響も出るんではないか。 現代俳句も、やはりおのれの枠を開放しなきゃいけないし、外から開放されることを迫られている時期でもあろうと思うんです。 それがプラスに働くことを期待します。 |
| リンズィー |
西洋の俳句雑誌でも、いい俳句がいっぱい出るんですが、ただ単にいい俳句ということで終わってしまう。 そういう実態があるのがもうわかっていて、アメリカの『TUNDRA』という雑誌では、短い詩は何でも、詩も短歌も俳句も同じ場に紹介して、お互いに刺激させるということをやっているんですよ。
|
| 藤田 |
ジャンルは超えられつつあるんですね。 |
| リンズィー |
はい。 すでに西洋でその動きがあります。 |
日本語で俳句をつくる外国人の仲間をもっとふやしたい |
|
| 藤田 |
ホームページに対する反応はどうですか。 |
| リンズィー |
結構いっぱいあるんですよ。 外国の雑誌からも、紹介したいから履歴と俳句を送ってくださいと依頼が来たりしますから、興味は持ってくれているみたいですね。 つい最近は、現代俳句協会のアメリカ版からの依頼で俳句を出しました。 そのとき、まず日本語ではなくて、初めて最初から英語で俳句をつくったんですよ。 俳句を教えてほしいという人も、何人もいます。 それで今、私が副編集長をやっている季刊『芙蓉』という俳句の雑誌で、外国人も参加して教えています。 でも、日本語で俳句をつくりたいという人は、今までにまだ2、3人ぐらいしかいないんです。 それがもっとふえたらなと思う。 前に、あるテレビ番組で、私やマブソンさんも含めた、外国人で日本語で俳句をつくっている人たちが5人ほど集まったことがあるんです。 お互いの句を選んで感想を言い合ったりしたんですが、非常におもしろかったですね。
ああいう仲間がもっと欲しいとマブソンさんとよく話しているんです。 日本語で俳句をつくる外国人、それは日本の俳句のためにもなると思うんです。
|
| 藤田 |
本当にいいお話を伺えました。 ありがとうございました |
| 宗 左近 (そう さこん) |
| 1919年福岡県生れ。 著書『詩[うた]のささげもの』 新潮社 2,100円(5%税込)、『小林一茶』 集英社(集英社新書) 777円(5%税込) ほか多数。 |
| Dhugal J. Lindsay (ドゥーグル・J・リンズィー) |
| 1971年オーストラリア生れ。 著書『句集むつごろう』 芙蓉俳句会 1,575円(5%税込)。 ※『句集むつごろう』は、有隣堂でのお取り扱いがございません。直接、芙蓉俳句会(TEL:03-3714-0276)にお問い合せください。 リンズィー氏の俳句ホームページ:Dhugal J. Lindsay's Haiku Universe (別ウィンドウでオープン) |
| 原 千代 (はら ちよ) |
| 1973年東京生れ。 |
|