| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |

| 平成16年1月1日 第434号 P1 |
|
|
||
| ○座談会 横浜駅物語 (1) (2) (3) |
P1 P2 P3 | |
| ○司馬史観と現代 | P4 | 磯貝勝太朗 |
| ○人と作品 横山秀夫と『影踏み』 | P5 | |
|
|
||
| 座談会 横浜駅物語 (1)
「みなとみらい線」開業にちなんで
|

|
| 右から岡田直氏、小林重敬氏、国吉直行氏と篠崎孝子 |
| ( |
◇初代横浜駅
明治5年 桜木町に誕生 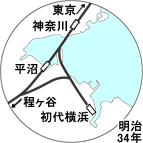 |
| 篠崎 |
まず、最初に鉄道が敷かれたことからご紹介いただけますか。 |
| 岡田 |
横浜駅は三回場所を移しています。一番最初の横浜駅は現在の桜木町駅の位置に、明治5年にできました。当時の海岸沿いに、東京から横浜の開港場を目指して線路が延びてきました。 駅は野毛浦の埋立地につくられました。ここは、関内地区から大岡川をはさんだ向かい側で、当時の市街地の外縁部と考えていいと思います。鉄道は、大体、明治時代に全国に敷かれていきますけれども、駅がつくられる場所は、基本的に市街地の外縁部になります。 当時の鉄道関係者の中に、明確な基準があったわけではないようですけれども、駅の位置を決めるときに一番重視されるのは、まず技術的な問題です。当時は今からは考えられないほど地形的な制約を受けます。大きな川が間にあったり、傾斜地だったりしたら駅はもうできないんです。 もう一つは経済的な合理性で、これは今も同じですが、市街地の真ん中に駅をつくるのは大変なんです。集落が幾つか点在している場合にも、それぞれの集落を一つ一つ結んで線路を敷き、駅をつくるのは非常に効率が悪い。明治時代にできる鉄道は、国土を貫く幹線ですから、真っすぐ敷くのが合理的なわけです。 そうすると、市街地の真ん中ではなくて、端っこか、場合によっては離れたところに駅ができていく。そういう観点から見て、横浜の場合、ちょうど市街地のへりの部分に駅ができたわけで、ごく標準的な姿だと思います。 |
鉄道ができると町がさびれるという伝説も |
|
| 岡田 |
資料がないんですけれども、実は大岡川を渡って関内の真ん中の住吉町のあたりに駅をつくる話もあったということを聞いたことがあるんです。 |
| 篠崎 |
反対の声があったんですか。 |
| 岡田 |
「鉄道忌避伝説」というのがありまして、鉄道ができることによって人がたくさん来て、町の風紀が乱れるとか、逆に人がどんどん出ていって町がさびれるとか、汽車が通ると煙が人体に害を及ぼすとかの理由で反対した。そのために駅が町から遠いところにできたという言い伝えが全国各地に残っているんです。例えば、藤沢や岡崎などがその典型です。ただし、真実かどうかは疑わしい。 横浜には、こういう伝説があったかどうかすらよくわからないのですが、横浜駅の場合は桜木町にできたのは極めて妥当なことでしょうから、「鉄道忌避伝説」で言われているようなことはなかったと考えていいと思います。 |
初代の駅舎は新橋駅と同じ形のペアの建物 |
|||
| 篠崎 |
鉄道建設の工事がたいへんだったようですね。 |
||
| 岡田 |
新橋からの鉄道線路は、ほぼ東海道に沿った形でつくられますが、神奈川のあたりから横浜駅までは大きな入江になっていたので、その入江を横切って、弓のような形に海面を埋め立てて線路が敷かれることになります。 明治3年に野毛浦の造成が終わり、その地続きの内田町から神奈川の青木町の間の埋立を請け負ったのが高島嘉右衛門です。東横線の高島トンネルの上に高島山がありますが、嘉右衛門はそこに自宅を構えて、工事の進捗状況を山の上から見ていたともいわれています。 今も残っている高島町という町名は、高島嘉右衛門の名前に由来しています。 |
||
| 国吉 |
最近、汐留の再開発でシオシティという街ができましたが、その事業の中で新橋ステーションが復元されております。昔の遺構が地下にちゃんと残っておりました。 明治3年にイギリスからエドモンド・モレルが招かれて鉄道事業を始めたときに、横浜駅と新橋駅の駅舎は、同じ形で、ペアでスタートしているわけです。 復元を担当した方々の話を聞きましたら、新橋駅は図面とか資料が余り残っていなかったそうです。それで横浜開港資料館が所蔵している写真などを参考にして、横浜駅とほぼ同じ形で新橋駅を復元しているんです。 |
||
| 岡田 |
横浜開港資料館にある『ファーイースト』に、新橋駅の写真が載っているんです。これは、明治初年に横浜居留地で発行された雑誌で、最近使わせてほしいという人が多いんです。 |
||
| 国吉 |
二つの駅が全く同じものだったということは、案外知られていないんです。建築をしたのはアメリカ人のブリジェンスです。モレルもブリジェンスも山手の外国人墓地に眠っています。ですから今、新橋で、最初の横浜駅の面影を見ることができるんです。 |
||
横浜と築地のふたつの居留地を約1時間で結ぶ |
|
| 小林 |
汐留と横浜に駅がなぜ立地したかというのは、よく言われることですが、お互いに居留地の玄関口ですね。築地の先に明石町の外国人居留地があって、東京の居留地と横浜の居留地をつなぐ役割を持っていた。 汐留も、昔の江戸から見ると、ちょっと辺ぴな土地だったと思うんです。ところがあの辺りは明治5年に大火が起きて、たまたま近くの汐留に駅があったので、そこを外国人向けの表玄関にしようということで、10数年かけて銀座煉瓦街づくりが行われます。今はありませんが、延長9キロにわたって煉瓦づくりの建物が並んでいたんです。その煉瓦街が、現在の銀座の素地になった。駅は辺境につくりましたが、そこが商業の中心になっていったんだと思います。 この大火のとき、横浜の方々が、銀座で罹災した人たちにかなりの義援金を贈っています。恐らく鉄道でつながったという意識があったんだと思います。鉄道建設がそういう結びつきを生んだということですね。 |
| 篠崎 |
できた当初は、どのくらい時間がかかっていたのでしょうか。 |
| 岡田 |
当時、新橋−横浜間を約1時間で結んでいます。当初は運転手も日本人ではなくて、お雇い外国人でした。 |
| 小林 |
どういう人たちが乗っていたかという記録はありますか。 |
| 岡田 |
正確なことはわかりません。やはり外国人向けという目的もあったと思うんですけれども、軍部は反対しているんです。明治5年にこんなことをやり出すよりも、軍備拡張のほうが先じゃないかということで、鉄道そのものに反対しているわけです。 汐留という場所にも、軍は反対しました。皇居の東側、江戸の下町ですね。こんなところではなくて、当時の山の手、江戸の範囲は市ヶ谷から四谷のあたりまでなんですが、そのもっと外側にすべきという意見が強かった。 必ずしも政府挙げて賛成していたわけではなかったという気がします。 |
スイッチバックせずに東海道線につなぐため平沼駅を開設 |
|||
| 岡田 |
横浜駅はその後、東海道線との関係がネックになります。東京−横浜の線路をつくったとき、将来、東京−大阪を結ぶ幹線の一部にしようという考えは、まだなかった。明治5年の段階では、東京−大阪間の鉄道は、中山道ルートにしようという考えだったんです。 東京−横浜はあくまでもその支線的な位置づけで、横浜から西に延ばしていく考えはなかったんですが、明治19年になって、中山道のルートは技術的に難しいということがわかってきまして、東海道に変更されるわけです。 ところが横浜駅は関内の市街地にぶつかるように駅をつくりましたから、スイッチバックするしかないんですね。 よく比較するのは大阪の駅のつくり方で、最初は神戸から大阪の市街地にぶつかり、スイッチバックで京都に向かう計画でしたが、それは不便だということで、急カーブですがスルー方式にした。それが梅田にできた大阪駅で、現在まで、その位置は変わっていないんです。 対照的に、横浜駅は二代目、三代目と移転せざるを得なくなっていきます。とりあえずスイッチバックで東海道線を延ばしましたが、当然不便なわけです。そこで神奈川と保土ヶ谷(程ヶ谷)の間に短絡ルートをつくろうということになります。要は、横浜駅に寄ってスイッチバックをせずに、直接神奈川から保土ヶ谷に行く。これは日清戦争のころに、軍用線として生まれます。その後、旅客線として使われるようになった。そうすると、横浜は全く無視された形になりますので、当然、反対の意見が起こってくるわけです。
それが明治29年で、折衷案で短絡線上に平沼駅が明治34年にできる。これは今、相鉄線の平沼橋駅のあるあたりです。横浜の人たちには、ここから汽車に乗って下さいというんですけれども、当時は市街地から離れ、全く不便なところなんです。 東海道線の大阪行きとか、神戸行きの列車が横浜を通らないわけですから、横浜駅の位置を何とかしてほしいということになって、駅舎の移転ということになるんです。大正4年に、高島町に二代目の横浜駅がつくられました。 |
||