| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |

| 平成16年1月1日 第434号 P2 |
|
|
||
| ○座談会 横浜駅物語 (1) (2) (3) |
P1 P2 P3 | |
| ○司馬史観と現代 | P4 | 磯貝勝太朗 |
| ○人と作品 横山秀夫と『影踏み』 | P5 | |
|
|
||
| 座談会 横浜駅物語 (2)
「みなとみらい線」開業にちなんで |
| ( |
◇二代横浜駅
大正4年高島町に移転 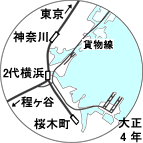
|
| 篠崎 |
二代目の駅はどんな駅だったのですか。最近、遺構が出てきましたね。 |
||
| 国吉 |
もともとこの辺にあるだろうということはわかっていたのですが、平成15年6月に、あるデベロッパーが整地しようとしていましたところ、地下に遺構の一部が発見されました。 駅の敷地は三角形の形をしております。これはなぜかと申しますと、一本は桜木町のほう、一本は東海道線の国府津のほうと、この駅から線路が二つに分かれているからです。駅が二つの方向を向いているということなんです。 非常に大がかりな駅で、煉瓦づくりの東京駅を彷彿させるような立派な建物です。しかし、大正12年9月の関東大地震の被害を受けたので、すごく寿命が短かった。わずか8年間でしたが、この駅が一番見栄えはよかったんじゃないかと言われているんです。 |
|
|
初代横浜駅は桜木町駅になり電車専用の線路に |
|
| 篠崎 |
高島町に横浜駅ができて、初代の横浜駅はどうなるんですか。 |
| 岡田 |
初代の横浜駅は桜木町駅という名前になったんです。駅名は、明治5年に初代横浜駅ができたときに、鉄道の柵の外側を桜木町と改称していますので、その町名に由来すると思います。 このころの鉄道は、蒸気機関車が引っ張っている汽車だったんですけれども、電車が走るようになるのが明治の終わりから大正のころなんです。一番早いのは現在の中央線、御茶ノ水から中野を走る当時の甲武鉄道です。明治37年に電車が走っています。路面電車ではなくて、普通の鉄道の線路の上を走る電車です。 東京−横浜間も東海道線の汽車はもちろん走っていますけれど、汽車は長距離の旅客を乗せるためのもので、通勤客や近距離の旅客は電車に乗せようということになるんです。電車専用の線路を東海道線に平行して敷いて、東京からまず高島町(二代目横浜駅)まで来て、高島町から桜木町までの線路は残ってますので、そこに、電車を走らせた。高島町と桜木町の間の線路は電車専用の線路になったんです。 |
| 篠崎 |
今の高架の線路ですね。 |
| 岡田 |
大正7年に、線路が高架になります。昭和39年まで、京浜東北線は大宮から来て桜木町で止まっていましたね。あの姿がこのときにできたんです。 |
| ◇三代横浜駅 昭和3年現在地に再移転 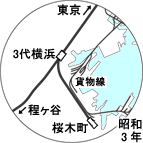
|
|
||
|
| 岡田 |
三代目の駅は、私鉄の乗り入れというのが特徴です。現在の横浜駅は東急、京急、相鉄と3つの私鉄が入ってますが、一つの駅に3つも私鉄が入ってくるのは、ほかに例がない。新宿は京王、小田急が入っていますが、西武はちょっと離れています。横浜駅は私鉄の乗り入れ数では日本で最多です。 当時で見ますと、東京横浜電鉄(現・東急)、神中鉄道(現・相鉄)、京浜急行は、品川側が当時京浜電鉄で、横須賀側は湘南電鉄、この4つの私鉄が入ってきたんです。 こんなにたくさんの私鉄が入ってきた駅は、当時としてもめずらしいんですが、最初からみんな横浜駅に入ることを目指していたわけではなかったんです。 |
4つの私鉄が結果的に横浜駅に集中 |
|||
| 岡田 |
東横電鉄は、建設が始まるのは二代目の駅が高島町にあったころで、大正15年に神奈川−丸子多摩川が開通します。ここから先は、二代目の横浜駅に入って国鉄に接続し、さらに桜木町、伊勢佐木町を通って鎌倉まで行こうとしていました。 京浜電鉄は、品川から神奈川まであった線路を横浜の都心のほうまで延ばしていこうとするんですが、横浜駅には接続せずに、神奈川から岡野町あたりをぐるっと回って、平沼、戸部を通って長者町を目指す計画だった。免許も取っていたんですけれども、神奈川駅の廃止ということがあって、東海道線との接続駅が失われてしまった。じゃあ三代目の駅に入れなさいよということになったわけです。 神中鉄道も、最初は保土ヶ谷に接続する予定だったんです。たまたま横浜駅の移転があって、近くなったからか、変更されている。 湘南電鉄は、最初、横須賀方面から黄金町まで来ていたんです。ここからは、桜木町につないで、桜木町を拠点にしようという案があったんです。結局これが実現せず、日ノ出町から戸部を通って、三代目横浜駅に入る。それで京浜電鉄に連絡するという今のルートに変わってしまったんです。 結果的に三代目横浜駅がここにできたおかげで、横浜近辺の私鉄が全部ここに集中するという、全国でも異例な形になってしまったんです。もしこの移転がなければ、また全然違う形態になっていたことが考えられます。 |
||
| 小林 |
当時の私鉄の性格ですけれど、今の旅客鉄道というイメージとは違って、貨物をベースにした部分もかなりあったんじゃないですか。それが結果的に旅客鉄道に変わっていったのではないか。 |
||
| 岡田 |
たしかに神中鉄道はもともと相模川の砂利を運ぶためのものですから、貨物鉄道の要素が強いんです。横浜駅に接続したことによって、沿線の人口がふえて、ディーゼルカーから電車になって、郊外電車になっていったんです。 郊外電車という言葉が当時あるんですけれど、これは市内の路面電車ではなくて、都市の外側に、郊外に延びていく電車のことです。郊外から都市へ、あるいは東京−横浜の間で人を運ぶ。東横や京浜、湘南は最初から郊外電車の要素のほうが強いですね。 |
||
| 小林 |
京浜急行は、京浜工業地帯の工業化との関連も考えられますよね。 |
||
| 岡田 |
工業地帯への通勤輸送という要素はありますね。 |
||
西口ダイヤモンド地下街誕生を機に駅が核となって発展 |
|
| 国吉 |
現在の横浜駅の周辺は、もともとは平沼という入り江だったんです。明治30年代まではずっとそういう状態が続いて、大正期に大体埋め立てが終わって、東口の出島地区周辺も大正期にできていますね。ですから、後背地がもともとなかったということだと思います。 かつて、西区のほうの最大の商店街は藤棚商店街だったと言われています。横浜の市電が浜松町から阪東橋へ走っていたんですが、昭和44年に廃止されてアクセスが不便になり、藤棚商店街はローカルなものに変わっていくわけです。一方、昭和39年には横浜駅西口にダイヤモンド地下街が誕生し、これを機に、横浜駅が核になって、大きく発展していくんですね。 乗降客数で見ますと、横浜駅は、関東では4番目、全国では3番目に梅田が入ってくるので、新宿、池袋、梅田、渋谷、横浜ということで5番目になります。 2000年の数字で、一日当たりの平均乗降者数は188万人を数える一大ターミナルです。 |
明治・大正期の駅前は地価も安く都市の中では場末 |
|
| 岡田 |
都市の中でどこが一番栄えているかを考えるときに、最も地価が高いところを求めれば、中心点が大体わかるんです。明治の横浜では、一番地価が高かったのは、弁天通りと馬車道の交差点のあたりなんです。これが大正に入ると、吉田町と伊勢佐木町の交差点に移る。 大正15年の土地の賃貸価格を見ますと、一番高い所は伊勢佐木町と吉田町で、桜木町駅前はその半分です。横浜駅前、つまり高島町のあたりはその三分の一程度です。ですから、駅前は当時の都市としては決して栄えたところではないわけです。明治、大正の都市にとって、駅前は場末の地というのが普通の姿だったと考えられるんです。 それから後は、長者町の交差点だったり、野澤屋(現・横浜松坂屋)の前だったりと、伊勢佐木町の中で転々と行き来はあるんですけれども、大体昭和30年代までずっと変わらないんです。 これが横浜駅の西口に移るのは昭和40年です。それ以来、横浜駅西口はずっとトップでして、例えば2003年の公示地価でいくと、一番高いところは一平方メートル当たり約350万円なんです。これが横浜市で最も地価の高いところです。 関内周辺は、尾上町も元町も一平方メートル当たり大体100数万円で、伊勢佐木町は100万円を切ってしまう。むしろ新横浜のほうが高いんです。現在は、地価から見れば完全に横浜駅西口の一極集中構造になっています。 三代目に移った当時の横浜駅周辺はさびれたところだったといわれますけれども、駅が町の中心になるのは、戦後の日本の都市の一般的な姿と考えていいと思います。 |